この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
36 正常圧水頭症患者の髄液排除試験(CSF タップテスト)後に実施する評価として適切なのはどれか。2つ選べ。
1.関節可動域
2.筋力
3.歩行能力
4.呼吸機能
5.認知機能
解答3/5
解説
髄液排除試験(CSF タップテスト)とは、正常圧水頭症の診断に使われる。検査前の症状の程度と比べて、検査後の症状が一時的に改善すれば、手術(髄液シャント術)による治療効果が期待できる。腰椎の間から過剰にたまっている脳脊髄液を少量排除して症状の改善具合を観察する検査である。正常圧水頭症の3大徴候として、①歩行障害、②尿失禁、③認知症がある。よって、選択肢3.5.歩行能力/認知機能が正しい。
1~2.4.× 関節可動域/筋力/呼吸機能は、正常であることが多い。
37 Duchenne型筋ジストロフィーのステージ(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)で、ステージの定義に記載のない動作はどれか。
1.階段昇降
2.椅子からの立ち上がり
3.膝歩き
4.四つ這い移動
5.座位保持
解答3
解説
1.〇 階段昇降は、ステージ1~2の定義に含まれる。
2.〇 椅子からの立ち上がりは、ステージ3の定義に含まれる。
3.× 膝歩きの定義はない。
4.〇 四つ這い移動は、ステージ5の定義に含まれる。
5.〇 座位保持は、ステージ7の定義に含まれる。
ステージ1 歩行可能 介助なく階段昇降可能(手すりも用いない)
ステージ2 階段昇降に介助(手すり、手による膝おさえなど)を必要とする
ステージ3 階段昇降不能 平地歩行可能 通常の高さのイスからの立ち上がり可能
ステージ4 歩行可能 イスからの立ち上がり不能
ステージ5 歩行不能 四つ這い可能
ステージ6 四つ這い不能だが、いざり移動可能
ステージ7 這うことはできないが、自力で坐位保持可能
ステージ8 ベッドに寝たままで体動不能 全介助
類似問題です↓
 【PT専門】筋ジストロフィーについての問題「まとめ・解説」
【PT専門】筋ジストロフィーについての問題「まとめ・解説」
38 一側の顔面神経麻痺の評価で優先度の低いのはどれか。
1.Synkinesis(随伴運動)の程度
2.前頭筋の筋力
3.咀嚼筋の筋力
4.味覚の程度
5.兎眼の程度
解答3
解説
1~2.〇 Synkinesis(随伴運動)の程度/前頭筋の筋力は、優先度は高い。なぜなら、顔面神経麻痺で、顔面筋の拘縮(前頭筋の筋力)、攣縮、連合運動(=随伴運動:Synkinesis)などを伴うため。しかし、前頭筋は両側の顔面神経から支配神経枝が出ているため、片側のみの麻痺では障害をきたさないことが多い。※顔面神経の中枢性麻痺の場合、前頭筋の障害は起こらないが、末梢性麻痺の場合は起こる。軸索の再生が、前とは違った筋や腺の支配神経域に向かって行われるとSynkinesis(随伴運動、病的共同運動)を生じる。ワニの涙症候群もこれにあたる。
3.× 優先度は低い。咀嚼筋は、三叉神経支配であるため、顔面神経麻痺では障害されにくい。
4~5.〇 味覚の程度/兎眼(眼瞼が閉じなくなり、眼球が常に露出する状態)の程度は、優先度は高い。味覚は、顔面神経が舌前2/3を支配する。兎眼の原因として、眼輪筋の麻痺があげられる。眼輪筋は表情筋の1つで、顔面神経支配である。両者とも、一側の顔面神経支配をうけるため、顔面神経麻痺で味覚障害/兎眼をきたす。
39 脳性麻痺痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。
1.重心の上下動が小さい。
2.骨盤の回旋が大きい。
3.股関節の内旋が大きい。
4.歩幅が大きい。
5.歩行率が小さい。
解答3
解説
両麻痺とは、両下肢に重度の麻痺がある状態のこと。
痙直型両麻痺の歩行(クラウチング歩行)は、股・膝とも屈曲位で伸びきらない歩行である。さらに、股関節は内転・内旋となるため内股での歩行が特徴的である。
1.× 重心の上下動は、「小さい」のではなく大きい。なぜなら、柔軟な動きが困難で尖足になりやすいため。
2.× 骨盤の回旋は、「大きい」のではなく小さい。なぜなら、骨盤・下肢の運動性と支持性が低下するため。
3.〇 正しい。股関節の内旋が大きい。股関節は内転・内旋しやすく、尖足になりやすい。
4.× 歩幅は、「大きい」のではなく小さい。なぜなら、下肢の可動域やバランス能力に制限があるため。ちなみに、歩幅とは、一側の踵が接地してから他側の踵が接地するまでの距離を示す。
5.× 歩行率が「小さい」と断言することは難しい(増加もしくは変化しないことが多い)。なぜなら、特に歩数は個人差が大きいため。下肢の可動域やバランス能力に制限があるため、新たな支持基底面の作成のため、「足をちょこちょこと早く出して、歩数が増える」場合もある。(※コメントありがとうございます。一方、コメントにて「歩数はバランスを取りながらなので単位時間内でそれほど多くの歩数を出せない」との声もありました。)もし、さらなる情報や参考文献をお持ちの方いらしたらコメントください。一応、「歩行率の著変な変化はない」と覚えていて問題ないかと思います(R6現在)。
苦手な方向けにまとめました。参考にしてください↓
40 運動学習の転移が関係していると考えられるのはどれか。
1.ゆっくりした歩行を練習した後に速い歩行が改善した。
2.温熱療法で痙縮を軽減させた後に階段昇降動作が改善した。
3.片麻痺患者にCI療法を行った後に麻痺側上肢の機能が向上した。
4.椅子からの立ち上がり練習を行った後に下肢伸筋群の筋力が向上した。
5.ハムストリングスを徒手的に伸張した後にプッシュアップ動作が改善した。
解答1
解説
運動学習とは、訓練や練習を通して獲得される運動行動の変化で、状況に適した協調性が改善していく過程である。
学習の転移とは、以前行った学習が、後に行う学習に影響を与えることである。
1.〇 正しい。ゆっくりした歩行を練習した後に速い歩行が改善した。前の学習が後の学習を促進しており、正の転移である。
2.× 温熱療法で痙縮を軽減させた後に、階段昇降動作が改善したのは、運動学習の転移とは関係が低い。温熱療法は物理療法であり、物理療法の効果で改善しているため不適切である。
3.× 片麻痺患者にCI療法を行った後に、麻痺側上肢の機能が向上したのは、運動学習の転移とは関係が低い。運動学習は、運動行動の変化であるため、麻痺側上肢の機能向上は運動学習とはいいにくい。ちなみに、CI療法とは、非麻痺側の運動を制限することで麻痺側の運動を促す方法である。
4.× 椅子からの立ち上がり練習を行った後に、下肢伸筋群の筋力が向上したのは、運動学習の転移とは関係が低い。運動学習は、運動行動の変化であるため、下肢伸展筋群の筋力向上は運動学習とはいいにくい。
5.× ハムストリングスを徒手的に伸張した後に、プッシュアップ動作が改善したのは、運動学習の転移とは関係が低い。ハムストリングスの徒手的伸張は、ストレッチ効果であるため、運動学習とはいいにくい。
類似問題です↓
 【PT/OT/共通】運動学習ついての問題「まとめ・解説」
【PT/OT/共通】運動学習ついての問題「まとめ・解説」

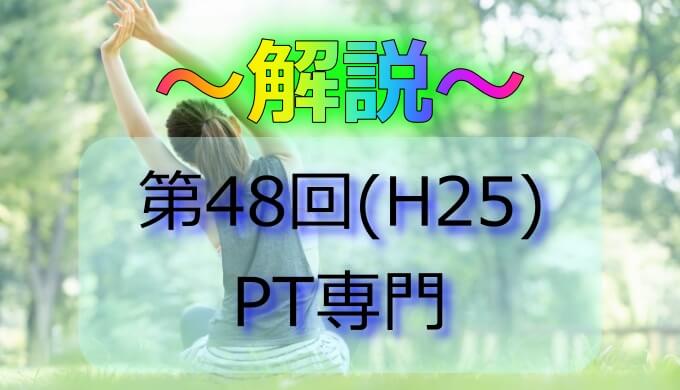

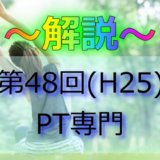
問39では脳性麻痺児は歩行率が上がるとありますが、実際に脳性麻痺児の歩行などを見ると歩数はバランスを取りながらなので単位時間内でそれほど多くの歩数を出せないと思っています。
脳性麻痺児はそれほど多く歩数を出して歩けるという解釈でしょうか。
コメントありがとうございます。
少し解説を修正致しましたのでご確認ください。
今後ともよろしくお願いいたします。
コメント失礼します。
問39の選択肢5番の解説にあります『歩数は減る為、歩行率が大きくなる』という解説内容が誤っているのではないかと思い、コメントさせていただきました。
正しくは『歩数が増える為、歩行率が大きくなる』であると思います。
ご返答お待ちしております。
コメントありがとうございます。
ご指摘通り間違えておりました。
修正致しましたのでご確認ください。
今後ともよろしくお願いいたします。