この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
96 てんかんで正しいのはどれか。
1.遺伝素因はない。
2.意識障害が必発する。
3.高齢発症は稀である。
4.病因は特発性と症候性に分けられる。
5.我が国の患者は約10万人と推定されている。
解答4
解説
1.× 遺伝素因はない「とは言いにくい」。てんかんには遺伝的素因が関与するタイプがあり、家族歴でリスクはやや上がる(2~10倍リスクが高い)。
2.× 意識障害は「必発ではない」。焦点発作や自律神経発作などは意識障害をともなわないてんかん(単純部分発作)もある。一方、強直間代発作などでは意識消失を伴う。
・焦点発作とは、Jackson発作ともいい、知能は正常で好発年齢・意識障害はないが、運動を司る大脳の一部が過剰に興奮することによって手や足が痙攣し、次第に全身の痙攣に発展してゆく発作である。
3.× 高齢発症は稀である「とはいえない」。てんかんの好発年齢は、小児期~思春期および老年期(60歳以降)で、二峰性である。
4.〇 正しい。病因は、①特発性(原発性:原因が不明)と、②症候性(続発性:原因が特定している)に分けられる。症候性の原因には、脳の先天奇形、脳腫瘍、脳血管障害、神経変性疾患などがあげられる。
5.× 我が国の患者は、「約10万人」ではなく、約100万人(有病率0.5~1%)と推定されている。
類似問題です↓
 【共通のみ】てんかんについての問題「まとめ・解説」
【共通のみ】てんかんについての問題「まとめ・解説」
97 統合失調症に特徴的な思考の障害はどれか。
1.思考が緩徐でうまく進まない。
2.思考の進行が突然遮断され、会話が停止する。
3.まわりくどく、要領よく思考目標に到達できない。
4.観念の間に論理的な関連がなく、意識の混濁を伴う。
5.観念が次々に沸き起こるが、つながりは表面的で目標から外れていく。
解答2
解説
統合失調症とは、幻覚・妄想・まとまりのない発語および行動・感情の平板化・認知障害ならびに職業的および社会的機能障害を特徴とする。原因は不明であるが、遺伝的および環境的要因を示唆する強固なエビデンスがある。好発年齢は、青年期に始まる。治療は薬物療法・認知療法・心理社会的リハビリテーションを行う。早期発見および早期治療が長期的機能の改善につながる。統合失調症患者の約80%は、生涯のある時点で、1回以上うつ病のエピソードを経験する。統合失調症患者の約5~6%が自殺し,約20%で自殺企図がみられる。したがって、うつ症状にも配慮して、工程がはっきりしたものや安全で受け身的で非競争的なものであるリハビリを提供する必要がある。
(※参考:「統合失調症」MSDマニュアル様HPより)
1.× 思考が緩徐でうまく進まないこと(思考制止)は、うつ病にも関連して起こる障害である。
2.〇 正しい。思考の進行が突然遮断され、会話が停止すること(思考途絶)は、統合失調症に特徴的な思考の障害である。
3.× まわりくどく、要領よく思考目標に到達できないこと(迂遠)は、認知症や高齢者、てんかんにみられる思考過程の障害である。
・迂遠とは、一つ一つの観念にとらわれてしまうために、その都度その観念に対する注釈を付け加えたり、言葉を変えたりして反復して話をするために思考が円滑に進まない状態。脳の器質的な原因によって生じる。
4.× 観念の間に論理的な関連がなく、意識の混濁を伴うこと(思考錯乱、アメンチア)は、せん妄などの器質性精神障害で起きやすい。統合失調症の滅裂思考は、意識は清明である。
5.× 観念が次々に沸き起こるが、つながりは表面的で目標から外れていくこと(観念奔逸)は、躁うつ病の特徴的な思考の障害である。
せん妄とは、疾患や全身疾患・外因性物質などによって出現する軽度~中等度の意識障害であり、睡眠障害や興奮・幻覚などが加わった状態をいう。高齢者は薬剤によってせん妄が引き起こされる場合も多い。
【原因】脳疾患、心疾患、脱水、感染症、手術などに伴って起こることが多い。他にも、心理的因子、薬物、環境にも起因する。
【症状】
①意識がぼんやりする。
②その場にそぐわない行動をする。
③夜間に起こることが多い。 (夜間せん妄)
④通常は数日から1週間でよくなる。
【主な予防方法】
①術前の十分な説明や家族との面会などで手術の不安を取り除く。
②昼間の働きかけを多くし、睡眠・覚醒リズムの調整をする。
③術後早期からの離床を促し、リハビリテーションを行う。
類似問題です。参考にどうぞ↓
98 摂食障害について正しいのはどれか。
1.摂食障害は女性のみに発症する。
2.神経性大食症は神経性無食欲症より有病率が高い。
3.神経性大食症では、自己誘発性嘔吐は認められない。
4.神経性大食症から神経性無食欲症に移行することはない。
5.神経性無食欲症では、過活動や運動強迫が認められない。
解答2
解説
1.× 摂食障害は「女性のみ」に発症するとはいえない(男性にも発症する)。ただし、男女比は1対10と女性に多い病気である。
2.〇 正しい。神経性大食症は神経性無食欲症より有病率が高い。一部の報告では、神経性大食症(2.32%)・神経性無食欲症(0.43%)というデータがある。※具体的な数値は調査や対象で幅があり、一例に過ぎず、普遍的な値ではない。
3.× 神経性大食症でも、自己誘発性嘔吐は「認められる」。自己誘発性嘔吐、下剤・利尿薬乱用、過度の運動や絶食といった不適切な代償行動がしばしばみられる。
4.× 神経性大食症から神経性無食欲症に移行すること「がある」。なぜなら、神経性大食症から神経性無食欲症とは共通の精神病理があるため。両者が依存したり神経性大食症から神経性無食欲症に移行する場合もある。
5.× 神経性無食欲症でも、過活動や運動強迫は「認められる」。なぜなら、病的な痩せ願望が根本にあるため。したがって、摂食障害の治療として、肥満への恐怖とボディーイメージのゆがみの矯正のために、認知行動療法が有効である。
摂食障害には、①神経性無食症、②神経性大食症がある。共通して肥満恐怖、自己誘発性嘔吐、下剤・利尿剤の使用抑うつの症状がみられる。作業療法場面での特徴として、過活動、強迫的なこだわり、抑うつ、対人交流の希薄さ、表面的な対応がみられる。患者の性格として、細かい数値へのこだわり(①体重のグラム単位での増減、②この食べ物はあの食べ物より〇カロリー多いなど)がみられる。
【摂食障害の作業療法のポイント】
①ストレス解消、②食べ物以外へ関心を向ける、③自信の回復(自己表出、他者からの共感、自己管理)、④過度の活動をさせない、⑤身体症状、行動化に注意する。
【性格的特徴】
①強情、②負けず嫌い、③執着心が強い、③極端な行動に及びやすい。
99 見捨てられ不安を特徴とするのはどれか。
1.依存性パーソナリティ障害
2.演技性パーソナリティ障害
3.回避性パーソナリティ障害
4.境界性パーソナリティ障害
5.自己愛性パーソナリティ障害
解答4
解説
1.× 依存性パーソナリティ障害とは、自分1人では何もできないという不安から他者に依存する傾向があり、過度に服従的である。ストレスを感じると自己犠牲的な行動に走ったり、すぐに安楽を求めるために悪癖に陥ることがあり、このような行動が、アルコールや薬物などの依存症につながることがあるとされている。また、依存性パーソナリティ障害の患者には、しばしば以下のうち1つ以上の病気もみられることが報告されている。①うつ病や持続性抑うつ障害などの抑うつ障害、②不安症、③アルコール使用障害、④別のパーソナリティ障害など。
2.× 演技性パーソナリティ障害とは、常に注目されていたいと願い、そうでない場合に抑うつ症状をきたす場合がある。感情表現が激しく話が誇張されていたり、関係性の割に馴れ馴れしい態度を取ったりする。
3.× 回避性パーソナリティ障害とは、内心は密接な対人関係を求めていながら、他者の批判や拒絶を気にするあまり、他者との関わりを避けることを特徴とする。
4.〇 正しい。境界性パーソナリティ障害は、見捨てられ不安を特徴とする。
・境界性パーソナリティ障害とは、感情の不安定性と自己の空虚感が目立つパーソナリティ障害である。こうした空虚感や抑うつを伴う感情・情緒不安定の中で突然の自殺企図、あるいは性的逸脱、薬物乱用、過食といった情動的な行動が出現する。このような衝動的な行動や表出される言動の激しさによって、対人関係が極めて不安定である。見捨てられ不安があり、特定の人物に対して依存的な態度が目立ち、他者との適切な距離が取れないなどといった特徴がある。【関わり方】患者が周囲の人を巻き込まないようにするための明確な態度をとる姿勢が重要で、また患者の自傷行為の背景を知るための面接が必要である。
5.× 自己愛性パーソナリティ障害とは、特権意識(自分が素晴らしいと誇大に思うこと)をもち、尊大で倣慢な態度(自己中心的な態度)をとる。賞賛されたいという欲求が強く、また他者への共感の感情が欠如する傾向を持つ。
類似問題です↓
 【共通のみ】パーソナリティ障害についての問題「まとめ・解説」
【共通のみ】パーソナリティ障害についての問題「まとめ・解説」
100 概日リズムの障害による疾患はどれか。
1.睡眠時遊行症
2.ナルコレプシー
3.睡眠相後退症候群
4.むずむず脚症候群
5.レム睡眠行動障害
解答3
解説
概日リズム睡眠障害とは、体内の睡眠・覚醒リズム(体内時計)が地球の明暗(昼夜)サイクルと一致していないときに起こる。原因として、脳の損傷、昼夜の周期に対する感受性の低下、長期間の寝たきり、不規則なシフトなどである。症状として、必要なときに眠ることができない(夜更かし)ため、昼間に眠くなり、意識の集中、明瞭な思考、日常活動などが困難になる。
1.× 睡眠時遊行症(夢遊病)は、睡眠中にもかかわらず体動が出現しぼんやりと歩き回る症状。 睡眠障害として睡眠時随伴症(パラソムニア)のひとつに分類される。小児に好発する。原因は、レム睡眠からの中途覚醒の異常(脳の部分的な覚醒)が背景とされ、睡眠不足・不規則生活・発熱・ストレス・アルコール・薬剤・睡眠時無呼吸などが誘因である。
2.× ナルコレプシーとは、日中の過度の眠気や、通常起きている時間帯に自分では制御できない眠気が繰り返し起こったり、突然の筋力低下(情動脱力発作)も伴う睡眠障害である。原因は、睡眠と覚醒のバランスを調整する役割を担うオレキシンの欠乏による可能性が高い。入眠時はレム睡眠となるため、入眠時の金縛り、中途覚醒、リアルな悪夢によってうなされることが多い。覚醒状態の維持やその他の症状(入眠時の幻覚、睡眠麻痺)をコントロールするために薬物療法を行う。
3.〇 正しい。睡眠相後退症候群は、概日リズムの障害による疾患である。
・睡眠相後退症候群とは、原因が、体内時計が遅れているため、睡眠が遅い時間帯のほうにずれてしまうことにある。症状として、明け方近くまで寝つけず、いったん眠ると昼過ぎまで目が覚めないという状態に陥る。無理をして起床すると、眠気や強い倦怠感などの症状がみられる。
4.× むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群、下肢静止不能症候群)は、身体末端の不快感(むずむず感)や痛みによって特徴づけられた慢性的な病態である。入眠時にむずむず感が生じると、それを軽減するために下肢を絶え間なく動かすために入眠が障害される。原因として、鉄欠乏性貧血、腎機能障害、透析患者などに多く見られ、日本において成人の3%程度に見られる。
5.× レム睡眠行動障害とは、レム睡眠の時に体が動く睡眠障害のことである。本来レム期に生じる筋無緊張が失われ、夢内容に沿った叫び・殴打・飛び起きなどがみられる。中高年男性に多く、パーキンソン病やレビー小体型認知症などでみられる。抗うつ薬で誘発・増悪あり。
※問題の引用:第55回理学療法士国家試験、第55回作業療法士国家試験の問題および正答について
※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。コメント欄にて誤字・脱字等、ご指摘お待ちしています。よろしくお願いいたします。

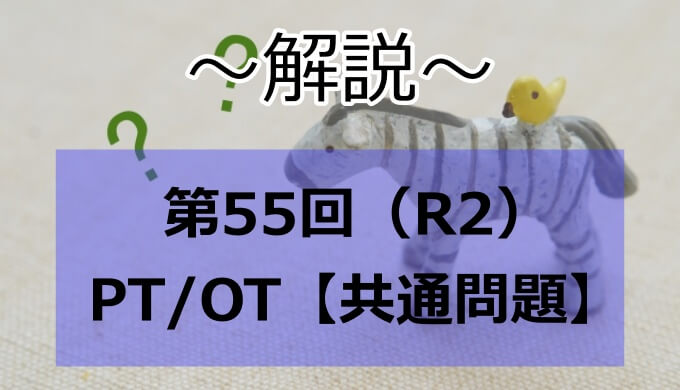
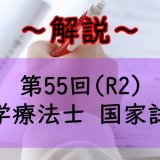
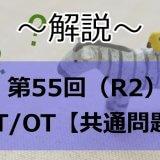
いつもありがとうございます。
コメントありがとうございます。
更新の励みになります。