この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
21 関節可動域測定時の足部の内転の基本軸はどれか。(※2022年改定)
1. 第1中足骨の中央線
2. 第1中足骨と第2中足骨との間の中央線
3. 第2中足骨の中央線
4. 第2中足骨と第3中足骨との間の中央線
5. 第3中足骨の中央線
解答3
(2022年足部の基本軸・移動軸が改訂されている)
解説
足部内転は、【基本軸】【移動軸】ともに第2中足骨長軸である。よって、選択肢3. 第2中足骨の中央線が正しい。ちなみに、【測定部位及び注意点】 膝関節を屈曲位, 足関節を0度で行なう。(※参考:「関節可動域表示ならびに測定法(2022年4月改訂)」公益社団法人 日本リハビリテーション医学会より)
覚えなおしたい方はこちら↓
22 筋とその短縮の有無を調べる検査との組合せで正しいのはどれか。
1. 腸腰筋 — Speedテスト
2. 縫工筋 — SLRテスト
3. 大腿直筋 — Thomasテスト
4. 大腿筋膜張筋 — Oberテスト
5. ハムストリングス — Thompsonテスト
解答4
解説
1. × Speedテスト(スピードテスト)は、「腸腰筋」ではなく、上腕二頭筋長頭腱の炎症の有無をみる。Speedテスト(スピードテスト)は、上腕二頭筋長頭腱の炎症の有無をみる。結節間溝部に痛みがあれば陽性である。【方法】被検者:座位で、上肢を下垂・肩関節外旋位から、上肢を前方挙上(肩関節屈曲)してもらう。検者:肩部と前腕遠位部を把持し、上肢に抵抗をかける。
2. × SLRテスト(下肢伸展挙上テスト)は、「縫工筋」ではなく、脊髄後根で圧迫を受ける疾患(坐骨神経痛、椎間板ヘルニアなど)の有無をみる。【方法】被験者は背臥位で、検者は被験者の下肢を持ち、膝関節伸展位のまま下肢を挙上し痛みの有無を確認する。痛みが生じたら陽性である。
3. × Thomasテスト(トーマステスト)は、「大腿直筋」ではなく、腸腰筋の短縮の有無を検査する。【方法】被験者は背臥位で、検者が被験者の検査側下肢の股関節を最大屈曲する。反対側の下肢の挙上があれば腸腰筋の短縮があると判断する。
4. 〇 正しい。Oberテスト(オーバーテスト)は、大腿筋膜張筋である。側臥位、膝関節屈曲位あるいは伸展位で、検査肢(上側の下肢)を下肢の自重で水平より降ろせない場合は陽性である。
5. × Thompsonテスト(トンプソンテスト)は、「ハムストリングス」ではなく、下腿三頭筋の断裂の有無を検査する。 腹臥位にて、膝屈曲位で下腿三頭筋を把持した際、足部の様子を観察する。反射的に足部が底屈すれば正常であり陰性、アキレス腱が断裂している場合には底屈せず陽性と評価する。
上腕二頭筋腱炎(上腕二頭筋長頭炎)は、上腕二頭筋長頭腱が、上腕骨の大結節と小結節の間の結節間溝を通過するところで炎症が起こっている状態のことである。腱炎・腱鞘炎・不全損傷などの状態で肩の運動時に痛みが生じる。Speedテスト(スピードテスト)・Yergasonテスト(ヤーガソンテスト)で、上腕骨結節間溝部に疼痛が誘発される。治療は保存的治療やステロイド局所注射となる。
23 健常者で最も歩行率が大きいのはどれか。
1. 5 歳
2. 10歳
3. 20歳
4. 40歳
5. 80歳
解答1
解説
歩行率(歩調、ケイデンスとも)とは、単位時間内(1分間)の歩数を表す。歩行率=歩数(歩)÷歩行時間(秒)で示され、一般的に幼児で高く(ヨチヨチ歩きで歩数が多いため)、年齢が高くなるにつれて減少していく。よって、選択肢1.5歳が選択肢の中で一番歩行率が大きい。
24 加齢に伴う生理的変化について正しいのはどれか。
1. 胸腺が肥大する。
2. 筋の収縮速度が速くなる。
3. 視覚の明順応時間は変化しない。
4. 筋量は下肢より上肢の方が減少する。
5. 低音域より高音域が聞こえにくくなる。
解答5
解説
1.× 胸腺が「肥大」ではなく萎縮する。なぜなら、加齢に伴い免疫力が低下するため。T細胞を作る役割を担う胸腺が年齢とともに退縮し、T細胞を増やす能力が低下する。 T細胞を産生する能力は、40歳代で新生児の100分の1まで低下するといわれている。
2.× 筋の収縮速度が「速くなる」のではなく遅くなる。筋の収縮速度(白筋)の特徴は、素早く収縮し大きな力の発揮することである。加齢に伴い、動作がゆっくりとなり、筋力の弱くなることが挙げられるが、その要因の一つに白筋の加齢に伴う減少が関係している。
3.× 視覚の明順応時間は「変化しない」のではなく、変化する(長くなる)。加齢に伴い、暗いところでも瞳孔がスムーズに動かなくなる。これを老人性縮瞳という。つまり、光を取り込みづらくなる場合があるため、暗いところでは若年層よりもさらにものが見えにくくなる。ちなみに、瞳孔は、暗いところでは、少ない光をできるだけ効率良く取り込めるようが開き、よりよく見えるように働いている。
4.× 逆である。筋量の減少は、「上肢」より「下肢」の方が大きい。なぜなら、下肢の方が筋肉量そのものが多いため。
5.〇 正しい。低音域より高音域が聞こえにくくなる。加齢性難聴は『感音性難聴』という種類の難聴に分類され、『感音性難聴』は鼓膜より内側の「内耳」や内耳以降の神経回路の部分による障害によって発生する難聴をさす。そのため、高齢者には低めの声で話しかけるとよい。また、生理的老化による感音性難聴により、弁別能の低下や高音域の聞き取りにくさがみられ、人との会話が聞き取りづらくなる。これにより、人と会ったり、外出したりすることを避けるようになり、外部との交流が途絶え、孤立につながるため、この状態が続くと社会的フレイルを招きやすい。
25 脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。
1. 内反尖足の予防
2. 立位感覚の向上
3. 覚醒レベルの向上
4. 体幹筋筋力の維持
5. 膝関節伸展筋の痙縮抑制
解答5
解説
①内反尖足の予防(足関節底屈筋群・アキレス腱の持続的伸長)
②立位感覚の向上
③覚醒レベルの向上
④体幹筋筋力の維持
他にも、起立性低血圧に対する漸進的順応・平衡感覚の再教育・血管拡張の保持・下肢(特に足関節)の拘縮予防・骨萎縮の予防・尿路感染の予防などがあげられる。(※参考:「理学療法訓練についての内容」別府重度障害者センター様HPより)
1~4.〇 斜面台を用いた運動療法の目的で、それぞれ内反尖足の予防になる/立位感覚の向上になる/覚醒レベルの向上になる/体幹筋筋力の維持は、脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的である。
5.× 膝関節「伸展筋」ではなく、「屈曲筋」の痙縮抑制に働く。痙縮の抑制には、関節可動域運動や伸長するとよい。つまり、膝関節伸展筋(抗重力筋)はより促通する可能性がある。
1. 片麻痺の痙縮に対して、ダントロレンナトリウム、チザニジン、バクロフェン、ジアゼパム、トルペリゾンの処方を考慮することが勧められる(グレードA)。顕著な痙縮に対しては、バクロフェンの髄注が勧められる(グレードB)。
2. 痙縮による関節可動域制限に対し、フェノール、エチルアルコールによる運動点あるいは神経ブロック(グレードB)およびボツリヌス療法(保険適応外)(グレードA)が勧められる。
3. 痙縮に対し、高頻度のTENS(transcutaneous electrical nerve stimulation:経皮的電気刺激)を施行することが勧められる(グレードB)。
4. 慢性期片麻痺患者の痙縮に対するストレッチ、関節可動域訓練が勧められる(グレードB)。
5. 麻痺側上肢の痙縮に対し、痙縮筋を伸長位に保持する装具の装着またはFES(functional electrical stimulation:機能的電気刺激)付装具を考慮しても良い(グレードC1)。
6. 痙縮筋に対する冷却または温熱の使用を考慮しても良いが、十分な科学的根拠はない(グレードC1)。
(※引用:「痙縮に対するリハビリテーション」脳卒中治療ガイドライン2009より)

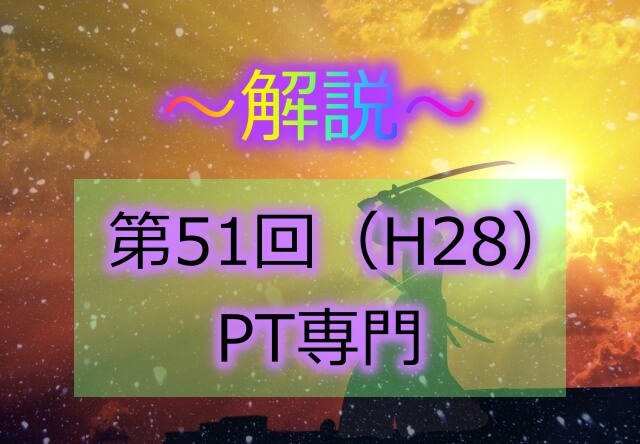



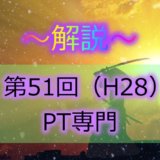
ROMは2022年の改訂から基本軸・移動軸が変わったので
21番は、「3. 第2中足骨の中央線」が今後正解になると思われます^^
コメントありがとうございます。
ご指摘通り確認したところ改定がありました。
覚えている限り反映させましたが、まだ直っていない箇所ありましたらお気軽にご連絡ください。
今後ともよろしくお願いいたします。