この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
61 副腎髄質から分泌されるホルモンはどれか。2つ選べ。
1.アドレナリン
2.アルドステロン
3.アンドロゲン
4.コルチゾール
5.ノルアドレナリン
解答1,5
解説
【副腎の構造】
・外側:副腎皮質(球状層・束状層・網状層)
・内側:副腎髄質(交感神経系と機能的に連動)
【副腎髄質ホルモン】
①アドレナリン、②ノルアドレナリン、③ドーパミン
→ これらを総称してカテコールアミンと呼び、ストレスや運動時に分泌され、心拍数増加・血圧上昇・血糖上昇などをもたらす。
1.〇 正しい。アドレナリンは、副腎髄質から分泌される。
・アドレナリンとは、腎臓の上にある副腎というところの中の髄質から分泌されるホルモンである。主な作用は、心拍数や血圧上昇などがある。自律神経の交感神経が興奮することによって分泌が高まる。
2.× アルドステロンは、副腎皮質から分泌される。
・アルドステロンとは、腎臓に作用してナトリウムと水の再吸収を促進し、循環血漿量増加を促し血圧を上昇させる。アルドステロンが過剰に分泌されると、高血圧や低カリウム血症、筋力低下などがみられる。
3.× アンドロゲンは、副腎皮質から分泌される。
・アンドロゲンとは、ステロイドの一種で、生体内で働いているステロイドホルモンのひとつである。アンドロゲンにはテストステロンとジヒドロテストステロン (dihydrotestosterone;DHT)があり、精巣の分化、機能、組織形成、さらに内性器・外性器の形成に重要な役割を果たす。
4.× コルチゾールは、副腎皮質から分泌される。
・コルチゾールとは、副腎皮質から分泌されるホルモンで、血糖値の上昇や脂質・蛋白質代謝の亢進、免疫抑制・抗炎症作用、血圧の調節など、さまざまな働きがあるが、過剰になるとクッシング症候群、不足するとアジソン病を引き起こす。
5.〇 正しい。ノルアドレナリンは、副腎髄質から分泌される。
・ノルアドレナリンとは、激しい感情や強い肉体作業などで人体がストレスを感じたときに、交感神経の情報伝達物質として放出されたり、副腎髄質からホルモンとして放出される物質である。ノルアドレナリンが交感神経の情報伝達物質として放出されると、交感神経の活動が高まり、その結果、血圧が上昇したり心拍数が上がったりして、体を活動に適した状態となる。副腎髄質ホルモンとして放出されると、主に血圧上昇と基礎代謝率の増加をもたらす。
62.骨格筋の筋収縮において筋小胞体から放出されたCa2+が結合するのはどれか。
1.アクチン
2.ミオシン
3.トロポニン
4.ミオグロビン
5.トロポミオシン
解答3
解説
①神経刺激が筋細胞膜を介して伝わり、筋小胞体からCa²⁺が放出される。
②放出されたCa²⁺はトロポニンに結合する。
③Ca²⁺が結合すると、トロポニンの構造が変化し、トロポミオシンがアクチンのミオシン結合部位から移動。
④ミオシン頭部がアクチンに結合できるようになり、ATP分解のエネルギーで首振り運動が起こる。
⑤アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの間を滑走して筋収縮が生じる。
1.× アクチンは、アクチンフィラメントを構成する(滑走に寄与)。
2.× ミオシンは、ミオシンフィラメントを構成する(首振り運動に寄与)。
3.〇 正しい。トロポニンが、骨格筋の筋収縮において筋小胞体から放出されたCa2+が結合する。
4.× ミオグロビンとは、筋内で酸素を貯蔵する色素タンパク質である。
5.× トロポミオシンは、アクチン上のミオシン結合部位を覆い、筋収縮を抑制する調節タンパク質である。
類似問題です↓
 【PT/共通】筋収縮の機序についての問題「まとめ・解説」
【PT/共通】筋収縮の機序についての問題「まとめ・解説」
63 交感神経の作用はどれか。
1.瞳孔を縮小させる。
2.排尿を促進させる。
3.気管支を拡張させる。
4.心拍数を減少させる。
5.胃腸の運動を促進させる。
解答3
解説
1.× 瞳孔を「縮小」ではなく 散大させる(瞳孔散大筋を収縮)。なぜなら、暗所や危険時に視野を広げるため。
2.× 排尿を「促進」ではなく抑制させる。
3.〇 正しい。気管支を拡張させる。なぜなら、酸素摂取を増やすため。
4.× 心拍数を「減少」ではなく増加させる。
5.× 胃腸の運動を「促進」ではなく抑制させる。
64 呼吸生理の説明で正しいのはどれか。
1.呼吸中枢は視床下部にある。
2.外肋間筋は安静呼吸の呼気筋として作用する。
3.内呼吸とは肺胞と毛細血管との間のガス交換をいう。
4.動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなる。
5.頚動脈小体は動脈血酸素分圧よりも動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすい。
解答4
解説
①安静吸気:横隔膜・外肋間筋。
②安静呼気:呼気筋は関与しない。
③努力吸気:呼吸補助筋(僧帽筋、胸鎖乳突筋・斜角筋・大胸筋・小胸筋・肋骨挙筋など)が関与。
④努力呼気:内肋間筋・腹横筋・腹直筋が関与。
1.× 呼吸中枢は、「視床下部」ではなく橋・延髄にある。呼気と吸気の交代とリズムの調節に関わるいくつかの機能を併せ持った複合的な中枢と考えられる。
2.× 外肋間筋は、肋骨を引き上げて胸郭を広げる(吸息する)よう働く(※解説上参照)。
3.× 内呼吸とは、細胞呼吸ともいい、組織と毛細血管との間のガス交換のことである。一方、外呼吸とは、肺胞と毛細血管との間のガス交換をいう。
4.〇 正しい。動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)が上昇すると、ヘモグロビンから酸素が解離しやすくなる。これをBohr効果(ボーア効果)といい、組織への酸素供給を促進する。
・ボーア効果とは、血液内の二酸化炭素量の変化による赤血球内のpHの変化によりヘモグロビンの酸素解離曲線が移動することである。ヘモグロビンの酸素解離曲線がpHの低下や温度上昇などの変化によって右方変移することで、末梢の酸素を解離しやすくなり、pHの上昇や温度低下などで左方偏移することで結合しやすくなる効果である。
・動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)とは、動脈血中の二酸化炭素の分圧を表す。
5.× 逆である。頚動脈小体は、「動脈血二酸化炭素分圧」よりも「動脈血酸素分圧」の変化を感知しやすい。なぜなら、末梢化学受容器(頸動脈小体と大動脈小体)は、動脈血酸素分圧の変化のセンサーとして機能しているため。これに対して、延髄ある中枢化学受容器は、主に動脈血二酸化炭素分圧の上昇に反応する。
65 血液凝固因子はどれか。2つ選べ。
1.アルブミン
2.トロンビン
3.ヘモグロビン
4.フィブリノゲン
5.エリスロポエチン
解答2,4
解説
血液凝固因子とは、Ⅰ:フェブリノーゲン、Ⅱ:プロトロンビン、Ⅲ:トロンボプラスチン、Ⅳ:カルシウムイオン、Ⅴ:プロアクセレリン、Ⅵ:(欠番)、Ⅶ:プロコンバーチン、Ⅷ:抗血友病因子、Ⅸ:クリスマス因子、Ⅹ:スチュアート因子、Ⅺ:PTA、Ⅻ:ハーゲマン因子、XIII:フェブリン安定化因子である。
1.× アルブミンとは、肝臓で作られるたんぱく質で、肝臓や栄養状態の指標となる。血清総蛋白の60%程度を占め肝臓で生成される。アルブミンが低値の場合は、低栄養状態、がん、 肝硬変など、一方で高値の場合は、脱水により血管内の水分が減少し、濃縮効果によることが考えられる。
2.〇 正しい。トロンビンは、血液凝固因子である。トロンビンとは、第II因子(プロトロンビン)の活性型で、フィブリノゲンをフィブリンに変換する。
3.× ヘモグロビンとは、酸素分子と結合する性質を持ち、肺から全身へと酸素を運搬する役割を担っている。
4.〇 正しい。フィブリノゲン(第I因子)は、血液凝固因子である。フィブリノゲンとは、血漿タンパクの一つであり、凝固因子の活性化によってフィブリンとなり、血液を凝固させる働きを持つ。増加した場合、血漿の粘稠度が上昇し血栓形成傾向を示す。 一方、低値の場合、播種性血管内凝固症候群(DIC)と肝機能障害が疑われる。
5.× エリスロポエチンエリスロポエチンとは、赤血球の産生を促進する造血因子の一つである。加齢に伴い、腎臓の機能が低下してエリスロポエチンの分泌が少なくなる。すると赤血球も減少するため、貧血症状があらわれやすくなる。

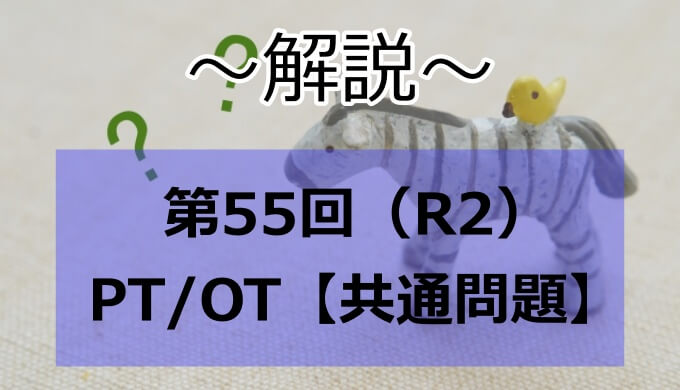
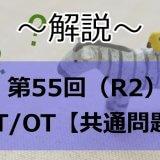
分かりやすい解説をありがとうございます。OT国試対策の参考にさせていただいております。
さて、本題に入りますが
61問「副腎皮質から分泌されるホルモンはどれか?2つ選べ」の問題…解答は1と5になっていますが、解説はすべてに置いて「副腎皮質から含まれる」となっております。解説を読み取りとなると全てが解の不適切問題ということになりますが、どうなのでしょうか?
コメントありがとうございます。ご指摘の点ですが、今回の解説では各選択肢ごとに「髄質から」「皮質から」と記載しており、内容としては正しいものとなっております。ただ、まとめ方によっては「全て皮質から」と誤解を招く表現に見えてしまったかもしれません。申し訳ありません。
改めて整理いたしますと、
・副腎髄質:アドレナリン(1)、ノルアドレナリン(5) → 正答
・副腎皮質:アルドステロン(2)、アンドロゲン(3)、コルチゾール(4)
となります。
引き続き、学習の参考にしていただければ幸いです。