この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
81 心理検査と評価内容の組合せとして適切なのはどれか。
1.SCT:認知機能
2.WCST:自我状態
3.P-Fスタディ:認知症介護負担度
4.Rorschach テスト:自己効力感
5.内田・クレペリン精神テスト:性格・行動面の特徴
解答5
解説
1.× SCTは、「認知機能」ではなく投影法の心理検査(性格検査の1つ)である。
・SCT(sentence completion technique:文章完成テスト)は、投影法の心理検査(性格検査の1つ)である。用紙にはいくつかの単語や不完全な文章があり、それらの続きを患者が完成させてもらうことで、人格を検査する。対象は小学生以上で、用紙は3種類あり、小学生・中学生・高校生以上用である。
2.× WCSTは、「自我状態」ではなく前頭葉認知度試験である。
・WCST(Wisconsin Card Sorting Test:ウィスコンシンカード分類テスト)は、前頭葉の機能を調べる検査であり、主に高次脳機能障害の評価に用いられる。4つの色と形が描かれた4枚のカードがあらかじめ並べられていて、被験者が手元にあるカードを分類カテゴリーに従って順次並べていくものである。
3.× P-Fスタディは、「認知症介護負担度」ではなく心理検査(性格特性を把握する検査)である。
・P-Fスタディ(Picture Frustration Study:絵画欲求不満テスト)は、欲求不満の場面の絵を24枚見せ、場面を想定して文章を書かせる投影法の心理検査(性格特性を把握する検査)である。欲求不満をどのように解決する傾向があるかをみる。
4.× Rorschach テストは、「自己効力感」ではなく投影法の性格検査である。
・Rorschach テスト(ロールシャッハテスト)は、投影法の性格検査である。10枚の図版(インクのシミ)を被験者に見せて、どのように見えるか答えさせ、そこから患者の知的側面と人格面を調べる。
5.〇 正しい。内田・クレペリン精神テストは、性格検査・職業適性検査の一種である。被験者に一定時間計算させ続けることで、作業量・集中力・注意力などの作業能力と、性格傾向を知ることができる。
82 切断後の幻肢で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.幼児の切断では強く現れる。
2.四肢末梢部ほど明確に感じる。
3.いったん出現した幻肢は消失しない。
4.術直後義肢装着法には予防効果がある。
5.上肢切断よりも下肢切断で強く現れる。
解答2,4
解説
1.× 幼児の切断では、「強く」ではなく少なく/弱く現れる。なぜなら、大脳の体性感覚野の形成が不十分であるため。したがって、4~6歳以下の小児切断例では出現しないことが多い。
2.〇 正しい。四肢末梢部ほど明確に感じる。指先・足趾など末梢ほど鮮明に感じやすい。なぜなら、大脳体性感覚野の領域が大きいため。
3.× いったん出現した幻肢は、「消失しない」といいきれない。むしろ、多くは時間とともに弱まる/短くなり、消失する例もある。
4.〇 正しい。術直後義肢装着法には予防効果がある。なぜなら、術直後義肢は、早期の視覚・体性感覚入力の統合や断端管理に寄与するため。したがって、幻肢痛の発現・持続の軽減に寄与するとされる。
5.× 逆である。「下肢切断」よりも「上肢切断」で強く現れる。なぜなら、大脳体性感覚野の領域が大きいため。
幻肢とは、幻肢痛ともいい、腕や足の切断後、失ったはずの感覚があり、かつそこに痛みを感じる状態である。切断をした人の約7割で生じるが、強い痛みは5~10%とまれである。幻肢痛のメカニズム(発生の機序)は解明されていない。下肢より上肢、近位部より遠位部に多く、電撃痛や、捻られるような痛み、ズキズキするような痛みなど様々である。一般的に、切断の手術後1週間以内に発症し、6か月~2年で消失することが多いが、それ以上長引くこともある。幻肢の大きさは健肢とほぼ同様で、幻肢痛が発生するのは、失った手や指、足などが多い。一方、肘や膝に感じることはまれで、4~6歳以下の小児切断例では出現しないことが多い。幻肢痛への一般的な治療方法として、薬物療法と非薬物療法に分けられる。幻肢痛は天候や精神的ストレスに左右されるため、薬物療法は、鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェン)、三環系抗うつ薬抗痙攣薬、プレガバリン(リリカ)などの抗てんかん薬が、神経痛の治療に使われる。非薬物療法としては、ミラーセラピーである。幻肢は断端の運動につれて移動し、断場の状態(神経や癒着など)に関連を持つ場合がある。
※幻肢痛は、心因性の要素が関係するため薬物療法以外の治療法 (バイオフィードバック、リラクセーション訓練、認知行動療法、経皮的電気神経刺激法【TENS】 など)も用いられる。ちなみに、ミラーセラピー(mirror therapy)とは、鏡を使用して運動の視覚フィードバックを与える治療法である。矢状面で両肢間に鏡を設置し、鏡に映された一側肢が鏡に隠れた反対側肢の位置と重なるようにする。切断や麻痺などの患側肢の遠位部に健側肢の映った鏡像がつながって見えることで、患側肢が健常な実像であるかのように感じさせながら運動を行う。
(※参考:「幻肢痛」慢性通治療の専門医による痛みと身体のQ&A様HPより)
83 Brown-Sequard 症候群で損傷髄節よりも下位の反対側に現れる症状はどれか。2つ選べ。
1.運動麻痺
2.触覚障害
3.痛覚障害
4.温度覚障害
5.深部覚障害
解答3,4
解説
Brown-Sequard 症候群(ブラウン・セカール症候群:脊髄半側症候群)は、損傷髄節よりも下位の反対側に温痛覚障害が生じ、同側に触覚の低下・痙性麻痺・深部感覚障害が生じる。
1.× 運動麻痺は、損傷髄節よりも下位の同側に見られる。
・皮質脊髄路は、錐体路とも呼ぶ。錐体路は、大脳皮質運動野―放線冠―内包後脚―大脳脚―延髄―錐体交叉―脊髄前角細胞という経路をたどる。
2.5.× 触覚障害/深部覚障害は、損傷髄節よりも下位の同側に見られる。
・後索路は、脊髄後角から同側の後索を通り、延髄でニューロンを換え、左右交差し、内側毛帯を通り、視床という経路となる。
3~4.〇 正しい。痛覚障害/温度覚障害は、損傷髄節よりも下位の反対側に現れる。
84 脊髄損傷で正しいのはどれか。
1.受傷直後は尿失禁状態となる。
2.排尿筋括約筋協調不全は生じない。
3.残尿が150mLでは導尿は不要である。
4.核・核下型神経因性膀胱であれば尿道カテーテル長期留置を行う。
5.核上型神経因性膀胱であればトリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みる。
解答5
解説
①肛門括約筋反射の消失
②膀胱・尿道の弛緩による完全尿閉
③神経原性の血管拡張による血液分布異常性ショック
④弛緩性麻痺
⑤深部腱反射・表在反射消失
1.× 受傷直後は、「尿失禁」ではなく尿閉状態となりやすい(脊髄損傷のショック期に見られる症状)。なぜなら、膀胱・尿道の反射が消失し弛緩性膀胱になるため。後に溢流性尿失禁が混じることはある。
2.× 排尿筋括約筋協調不全は「生じる」。なぜなら、慢性期の核上型(脊髄円錐より上位)では膀胱は過反射的に収縮する一方、外尿道括約筋は同時に過緊張しやすく、高圧排尿・残尿増加を招くため。
3.× 残尿が150mLでは導尿は、「必要」である。なぜなら、残尿は100ml以上にて異常と判断することが多いため。したがって、膀胱過伸展や感染を防ぐため間欠導尿を行う。
4.× 核・核下型神経因性膀胱では、尿道カテーテル長期留置を行う優先度は低い。なぜなら、膀胱は弛緩して大量残尿・溢流性尿失禁になりやすいため。したがって、清潔間欠自己導尿が泰一優先される。
5.〇 正しい。核上型神経因性膀胱であれば、トリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みる。なぜなら、膀胱が過反射で小容量・頻回排尿になりやすく、皮膚刺激(恥骨上部の軽打など)で排尿反射を誘発できる場合があるため。
・核上型膀胱(反射型または痙性膀胱)とは、受傷前の膀胱のためられる尿量が少なくなる傾向になる状態である。ちょうど他の筋肉に痙性が出現し、独自で収縮するのと同様に、膀胱の筋肉にも痙性が起こり得る。その結果、排尿は頻回で少量になる。この膀胱のタイプは、仙髄レベルより上位の受傷では一般的になる。そのため、核上型神経因性膀胱であればトリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みる。
核型・核下型膀胱とは、弛緩性膀胱ともいい、膀胱筋は収縮する能力を失い、弛緩しやすくなるため、尿が多量に膀胱にたまりがちになる状態のこと。筋肉が収縮できないので、膀胱が過膨張した(たまりすぎた)結果として、尿が膀胱から出てくる。尿は水がいっぱい入りすぎたグラスのようにあふれてこぼれる。この膀胱のタイプは、仙髄レベルか馬尾損傷の脊髄損傷で一般的にある。膀胱が充満する感覚は障害されている。そのため、核・核下型神経因性膀胱であれば、清潔間欠自己導尿や投薬、排尿の時に膀胱の収縮力を上げる治療、電気刺激により排尿を誘発する方法などを行う。
類似問題です↓
 【共通のみ】ショックについての問題「まとめ・解説」
【共通のみ】ショックについての問題「まとめ・解説」
85 診断においてMRI拡散強調像が最も有用なのはどれか。
1.頭蓋底骨折
2.脳室内出血
3.脳梗塞急性期
4.脳出血急性期
5.くも膜下出血急性期
解答3
解説
拡散強調像(DWI画像)は、発症後1~3時間以内の超急性期の梗塞巣を確認できるとされる。なぜなら、水分子の拡散運動(自由運動度)を画像化したものであるため。拡散が低下した領域が高信号として描出される。発症から4~5時間以内の脳梗塞に対しては、血栓溶解療法(t-PA療法)という治療が行われる。初期対応は予後に大きく関わるため迅速に対応する必要がある。
1.× 頭蓋底骨折は、レントゲン検査やCT検査で行う。
・CT検査とは、脳内の腫瘍や出血などの異常の有無や程度が分かる。出血部位(急性)は高吸収域(白)としてうつる。エックス線を使用した撮影である。
2.× 脳室内出血は、レントゲン検査やCT検査で行う。
・脳室内出血とは、様々な原因に伴い、脳室の内部に血腫が流れ込んだ状態である。
3.〇 正しい。脳梗塞急性期は、MRI拡散強調像が最も有用な診断である。
・脳梗塞とは、何らかの原因で脳の動脈が閉塞し、血液がいかなくなって脳が壊死してしまう病気である。どの動脈による閉鎖なのかによって、症状は異なるが、片方の手足の麻痺やしびれ、呂律が回らない、言葉が出てこない、視野が欠ける、めまい、意識障害など様々な症状が出現する。
4~5.× 脳出血急性期/くも膜下出血急性期は、レントゲン検査やCT検査で行う。
・くも膜下出血とは、くも膜と呼ばれる脳表面の膜と脳の空間(くも膜下腔と呼ばれ、脳脊髄液が存在している)に存在する血管が切れて起こる出血である。くも膜下出血ではくも膜下腔に血液が流入し、CTでは高吸収域として抽出される。合併症には、①再出血、②脳血管攣縮、③正常圧水頭症などがある。①再出血:発症後24時間以内が多く、死亡率も高い。②脳血管攣縮:72時間後〜2週間後(ピークは8〜10日)が多く、脳血管攣縮による梗塞の好発部位は、「前交通動脈」である。③正常圧水頭症:数週〜数ヶ月後に認知症状、尿失禁、歩行障害などの症状が出現する。
核磁気共鳴画像法(MRI)とは、核磁気共鳴現象を利用して生体内の内部の情報を画像にする方法である。治療前にがんの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認するなど、さまざまな目的で行われる精密検査である。
①拡散強調像(DWT):超急性期(発症後1~3時間)
②FLAIR像:発症後3~6時頃
③T2強調像:発症後3~6時頃
④T1強調像の順である。

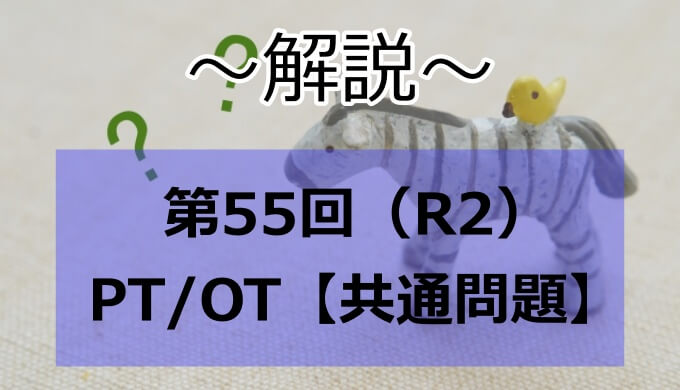
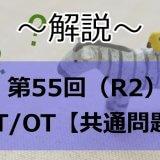
ブラウン・セカール症候群についての問題。教科書や他の参考書を見ても、(反対側で)温痛覚の障害は出ると書かれております。でも触覚障害はどの教科書もあり得ないと書かれています。これが納得できないです。通り道的にこれも正解で良くないでしょうか?
コメントありがとうございます。
教科書に「触覚障害はどの教科書もあり得ない」と書かれていた場合は、確かに理解に混乱が生じるかもしれません。
結論から言うと、試験や教科書でいう「触覚」は単一の神経路ではなく、後索路(精細触覚)と前脊髄視床路(粗大触覚)という二重の経路で伝導されているため、Brown–Séquard症候群では臨床的・教育的に「触覚障害あり」とは扱われません。
具体的には、前脊髄視床路は脊髄レベルで交叉するため、理論上は反対側の触覚低下が起こり得ます。しかし後索路は同側を上行して機能が保たれるため、触覚は全体として保たれやすく、診断上の特徴にはなりません。一方、痛覚・温度覚は脊髄視床路のみを通り、代替経路が乏しく交叉も早いため、反対側に明瞭な障害が出現します。このため、神経解剖学的には触覚低下を考え得るものの、試験や教科書では「反対側は温痛覚障害のみ」と整理されています。
ロールシャッハテストはインクのシミのやつではないですか?
コメントありがとうございます。
ロールシャッハテストはインクのシミのやつです。