この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
76 悪性腫瘍細胞の特徴で誤っているのはどれか。
1.増殖が速い。
2.核分裂が多い。
3.染色体異常が多い。
4.核/細胞質比が小さい。
5.未分化型は悪性度が高い。
解答4
解説
1~3.5.〇 悪性腫瘍の特徴(増殖が速い。核分裂が多い。染色体異常が多い。未分化型は悪性度が高い。)として正しい。
4.× 核/細胞質比が小さいのは良性腫瘍の特徴である。
・核 / 細胞質比とは、1つの細胞の「核の面積」を「細胞質の面積」割ったものである。つまり、細胞における核の面積割合のこと。悪性腫瘍細胞は、活発に分裂すると核や細胞の形がイビツになり、核の面積が大きいのも特徴である。つまり、核/細胞質比は大きくなる。
77 ステロイド薬の長期投与によって生じやすいのはどれか。
1.腎不全
2.低血圧
3.骨粗鬆症
4.体重減少
5.高カリウム血症
解答3
解説
【ステロイドの機序】
ステロイドは細胞の中に入った後にグルココルチコイド受容体に結合する。ステロイドの結合したグルココルチコイド受容体は、細胞の核内へ移行し、炎症に関与する遺伝子の発現を調節すると言われている。 この結果として強力な抗炎症作用と免疫抑制作用が発揮される。
【ステロイドの副作用】
軽度:中心性肥満、体重増加、満月様顔貌
重度:消化管潰瘍、糖尿病、感染症、骨粗鬆症・骨壊死、筋炎、精神症状(抑うつ、せん妄)
ステロイドを長期的に内服した場合、体内でステロイドホルモンが分泌されなくなることがある。そのため、急に薬の内服を止めると体内のステロイドホルモンが不足し、倦怠感や血圧低下、吐き気、低血糖などの症状が起こることがある。これをステロイド離脱症候群という。
(※参考:「副腎皮質ステロイド」日本リウマチ学会様HP)
1.× 「腎不全」ではなく副腎不全を引き起こす。
2.× 「低血圧」ではなく高血圧を引き起こす。
3.〇 正しい。骨粗鬆症は、ステロイド薬の長期投与によって生じやすい。
4.× 「体重減少」ではなく体重増加を引き起こす。
5.× 「高カリウム血症」ではなく低カリウム血症を引き起こす。
78 良性の骨軟部腫瘍はどれか。
1.脊索腫
2.軟骨肉腫
3.血管内皮腫
4.海綿状血管腫
5.多発性骨髄腫
解答4
解説
骨軟部腫瘍とは、骨や筋肉、脂肪、血管、神経、靱帯などの「骨」および「軟部組織」に発生する腫瘍の総称である。良性と悪性があり、悪性のものは「骨肉腫」や「脂肪肉腫」などの肉腫と呼ばれる。良性腫瘍は、増殖が遅く転移もしないが、悪性は周囲組織に広がりやすく、血行性に肺などへ転移することがある。症状はしこり、痛み、腫れ、関節の動きにくさなどで、初期は無症状の場合も多い。
1.× 脊索腫(せきさくしゅ)は、悪性の骨軟部腫瘍である。本来なくなるはずの脊索の一部が頭の中に残り、腫瘍になったものである。脊椎や頭蓋底の骨(斜台)から発生し、小児にも成人にもみられる。
2.× 軟骨肉腫は、悪性の骨軟部腫瘍である。最低限、「肉腫=悪性」は覚えておく。
・軟骨肉腫とは、組織学的に腫瘍性の軟骨形成を伴うが、腫瘍性の類骨・骨形成を伴わない悪性骨腫瘍と定義される。つまり、軟骨肉腫は、他の多くの骨腫瘍と異なる。腫瘍は遅く成長し、薬物が適切に浸透しないため化学療法に感受性の低く、手術が主な治療法となる。
3.× 血管内皮腫は、血管肉腫と血管腫の中間の悪性度を示す。転移例もあるため良性とはいえない。
4.〇 正しい。海綿状血管腫は、良性の骨軟部腫瘍である。悪性化はしないが、ゆっくり増大したり部位によっては疼痛・出血などの症状を来すことがある。骨・皮膚・肝・軟部など多部位にみられる。男女差はなく、20~40歳代に発症することが多い。
5.× 多発性骨髄腫は、悪性の形質細胞腫瘍(造血器腫瘍)である。形質細胞がクローン性に増殖するリンパ系腫瘍である。増殖した形質細胞やそこから分泌される単クローン性免疫グロブリンが骨病変、腎機能障害、M蛋白血症などさまざまな病態や症状を引き起こす。多発性骨髄腫の発症年齢は65~70歳がピークで男性が女性より多く約60%を占める。腫瘍の増大、感染症の合併、腎不全、出血、急性白血病化などで死に至る。
79 転移・逆転移で適切なのはどれか。
1.陰性転移の解釈は避ける。
2.転移は逆転移を誘発する。
3.逆転移は治療の阻害因子となる。
4.逆転移は治療者の意識的反応である。
5.心理治療の目標は陽性転移の出現である。
解答2
解説
転移と逆転移は、精神分析療法の上で重要な概念である。
①転移:患者が今までの生活史における重要人物(親、学校の先生)に示してきた感情や態度を治療者に向けること。
②逆転移:治療者が患者に向けることである。
その感情が愛情などプラスのものである場合を陽性転移、憎悪などマイナスのものである場合を陰性転移という。
1.× 陰性転移の解釈は避ける必要はない。なぜなら、陰性・陽性いずれも患者理解の重要な臨床情報として役立つため。したがって、「避ける」のではなく適切なタイミングと強度で解釈する。
2.〇 正しい。転移は逆転移を誘発する。なぜなら、転移・逆転移は心理治療でよく起こることであるため。
3.× 必ずしも、逆転移は治療の阻害因子となる「とはいえない」。なぜなら、治療者自身で解決・相談することもできるため。また、気づきや内省により臨床的資源となることもある。
4.× 逆転移は治療者の「意識的反応」ではなく無意識的反応である。これに関して、精神科医のユングは、個人の無意識のさらに下に、人類に共通する「集合的無意識」があることを提唱した。
5.× 心理治療の目標は、「陽性転移の出現」ではなく「症状・葛藤の軽減と人格機能の改善」である。陽性転移は、治療の継続の支えになることもあるが、出現それ自体が目的ではない。
80 Eriksonによる成人中期の心理的発達課題はどれか。
1.勤勉性
2.同一性
3.親密性
4.生殖性
5.自我の統合
解答4
解説
乳児期(0歳~1歳6ヶ月頃):基本的信頼感vs不信感
幼児前期(1歳6ヶ月頃~4歳):自律性vs恥・羞恥心
幼児後期(4歳~6歳):積極性(自発性)vs罪悪感
児童期・学童期(6歳~12歳):勤勉性vs劣等感
青年期(12歳~22歳):同一性(アイデンティティ)vs同一性の拡散
前成人期(就職して結婚するまでの時期):親密性vs孤立
成人期(結婚から子供が生まれる時期):生殖性vs自己没頭
壮年期(子供を産み育てる時期):世代性vs停滞性
老年期(子育てを終え、退職する時期~):自己統合(統合性)vs絶望
1.× 勤勉性は、児童期・学童期である。
2.× 同一性は、青年期である。
3.× 親密性は、前成人期である。
4.〇 正しい。生殖性は、成人中期である。
5.× 自我の統合は、老年期である。

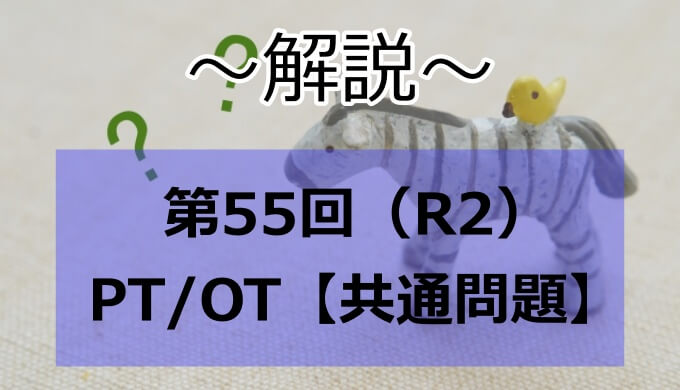
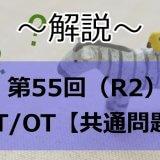
はじめまして。いつもこちらのサイトにて勉強させていただいております。わかりやすくて詳しい解説、ありがとうございます。
国試過去問を確認したところ、第55回 R2年 PM76の選択肢は、下記のようになるかと思います。
誤 4.細胞質比が小さい。
正 4.核/細胞質比が小さい。
ご確認よろしくおねがいします。
コメントありがとうございます。
ご指摘どおり間違えておりました。
修正いたしましたのでご確認ください。
今後とも何卒よろしくお願い致します。
迅速なご対応ありがとうございました。
これからもどうぞ宜しくおねがいします。