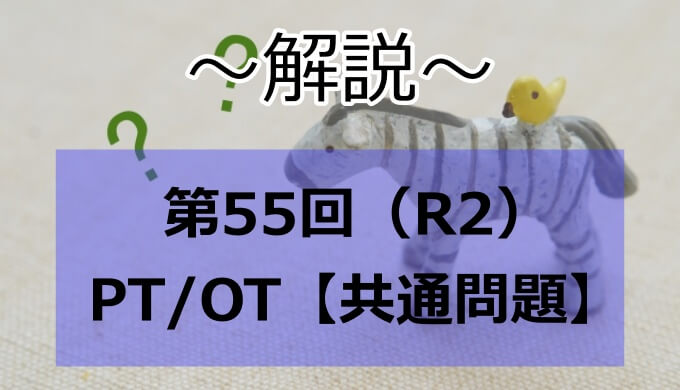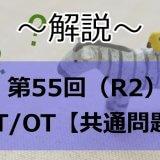この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
91 β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に最も適している指標はどれか。
1.PCI
2.Borg指数
3.Karvonen法
4.安静時心拍数
5.最大予測心拍数
解答2
解説
β遮断薬とは、主に高血圧や狭心症、不整脈(特に、心房細動)の治療に用いられる。交感神経を抑制し、慢性心不全の進行を防ぐ。つまり、β遮断薬は「心拍数の低下作用」がある。
1.× PCI(Physiological cost index:生理的コスト指数)は、心拍数に依存する指標であるためβ遮断薬服用中患者(心拍数上昇が鈍化)には適さない。
・PCI(Physiological cost index:生理的コスト指数)とは、運動前の安静時心拍数と最適負荷での運動時の心拍数を速度または頻度で除したもので、値が小さいほど運動効率が良いとされる簡易的な運動耐久性指標である。成人の歩行においては0.1~0.3beat/meterが標準値とされている。
2.〇 Borg指数が、β遮断薬服用中患者の運動負荷量決定に最も適している指標である。なぜなら、息切れ・きつさ等の自覚に基づくため。したがって、心拍反応が変化していても負荷調整に有効である。
・Borg指数(ボルグ指数)は、主観的運動強度、自覚的運動強度(RPE:rating of perceived exertion)とも呼ばれ、運動したときのきつさを数字と簡単な言葉で表現し、標準化したものである。Borg指数(ボルグ指数)は、自覚的な症状も対応できる。
3.× Karvonen法(カルボーネン法)は、心拍数に依存する指標であるためβ遮断薬服用中患者(心拍数上昇が鈍化)には適さない。
・Karvonen法(カルボーネン法)は、年齢や安静時心拍数から運動強度を算出するときに使用される。「(220-年齢)-安静時心拍数)×運動強度(%)+安静時心拍数」で求めることができる。
4.× 安静時心拍数は、心拍数に依存する指標であるためβ遮断薬服用中患者(心拍数上昇が鈍化)には適さない。
5.× 最大予測心拍数は、心拍数に依存する指標であるためβ遮断薬服用中患者(心拍数上昇が鈍化)には適さない。
・最大予測心拍数とは、「最大心拍数=220-年齢」で一般的に求めることができる。高齢者の場合は、「最大心拍数=207-(年齢×0.7)」の式を用いる方法もある。
92 血友病の臨床症状で最も多いのはどれか。
1.関節内出血
2.血小板数減少
3.出血時間延長
4.毛細血管拡張
5.リンパ節腫脹
解答1
解説
1.〇 正しい。関節内出血は、血友病の臨床症状で最も多い。なぜなら、血友病は、凝固因子欠乏による二次止血(凝固)の障害であるため。一方、一次止血が主因の疾患で目立つ粘膜出血や出血時間延長は典型的ではない。
・関節内出血とは、関節に出血がたまる状態である。痛み・腫脹・熱感・可動域制限を呈しやすい。
2.× 血小板数は、「減少」ではなく正常である。なぜなら、血小板は一次止血に寄与するため。
・血小板とは、血液凝固や止血に重要な働きをする。
3.× 出血時間は、「延長」ではなく正常である。出血時間の延長は、一次止血障害で見られる。
4.× 毛細血管拡張は、遺伝性出血性毛細血管拡張症などでみられる。
5.× リンパ節腫脹は、感染や腫瘍性病変などでみられる。
・リンパ節腫脹とは、1つまたは複数のリンパ節が増大して触知できるようになった状態である。ウィルス、細菌、結核菌、梅毒、トキソプラズマなどによって起こる。体表から触知できるリンパ節は、①頭頸部、②腋窩、③肘関節上部、③腹部、④鼠径部(大腿部)、⑤膝窩部である。リンパ節は皮下に存在するため、皮膚を動かしても皮膚と一緒に動くことはないため、示指から環指の指腹を皮膚に軽く密着させ、皮膚を動かすことにより触診する。
血友病とは、血液を固めるのに必要な「血液凝固因子(第Ⅷ因子または第Ⅸ因子)が不足・活性低下する病気のことである。
【概念】
伴性劣性遺伝(男児に多い):生まれつき発症することがほとんどであるため、幼少期から①些細なことで出血する、②出血が止まりにくいといった症状が繰り返される。
血友病A:第Ⅷ凝固因子の活性低下
血友病B:第Ⅸ凝固因子の活性低下
【症状】関節内出血を繰り返し、疼痛、安静により関節拘縮を起こす。(筋肉内出血・血尿も引き起こす)肘・膝・足関節に多い。鼻出血、消化管出血、皮下出血等も起こす。
【治療】凝固因子製剤の投与、関節拘縮・筋力低下に対するリハビリテーション
(※参考:「血友病」Medical Note様HP)
93 多発性骨髄腫に特徴的でないのはどれか。
1.貧血
2.腎障害
3.易感染性
4.病的骨折
5.低カルシウム血症
解答5
解説
多発性骨髄腫は形質細胞がクローン性に増殖するリンパ系腫瘍である。増殖した形質細胞やそこから分泌される単クローン性免疫グロブリンが骨病変、腎機能障害、M蛋白血症などさまざまな病態や症状を引き起こす。多発性骨髄腫の発症年齢は65~70歳がピークで男性が女性より多く約60%を占める。腫瘍の増大、感染症の合併、腎不全、出血、急性白血病化などで死に至る。
主な症状として、頭痛、眼症状の他に①骨組織融解による症状(腰痛・背部痛・圧迫骨折・病的骨折・脊髄圧迫症状・高カルシウム血症など)や②造血抑制、M蛋白増加による症状(貧血・息切れ・動悸・腎機能障害)、易感染性(免疫グロブリン減少)、発熱(白血球減少)、出血傾向(血小板減少)などである。
1.〇 貧血は、多発性骨髄腫にみられる。なぜなら、造血抑制(骨髄浸潤)によるため。
2.〇 腎障害は、多発性骨髄腫にみられる。なぜなら、M蛋白が尿細管を詰まらせ毒性を与えるため。
3.〇 易感染性は、多発性骨髄腫にみられる。なぜなら、腫瘍性形質細胞が異常な単クローンIgを作る一方、正常Ig産生が抑えられるため。つまり、免疫不全が生じる。
4.〇 病的骨折は、多発性骨髄腫にみられる。なぜなら、溶骨性病変に伴うため。脊椎圧迫骨折・肋骨骨折が典型。
5.× 低カルシウム血症は、多発性骨髄腫に特徴的でない。多発性骨髄腫では、骨破壊による高カルシウム血症が起こる。
94 2型糖尿病患者における運動療法の効果で誤っているのはどれか。
1.インスリン抵抗性の増大
2.血圧低下
3.血糖コントロールの改善
4.脂質代謝の改善
5.心肺機能の改善
解答1
解説
1.× インスリン抵抗性の「増大」ではなく改善する効果が2型糖尿病患者における運動療法にある。なぜなら、適度な運動療法は、骨格筋での非インスリン依存的な糖取り込みを増やすため。
2.〇 血圧低下は、運動療法の効果である。なぜなら、内皮機能改善・交感神経活動抑制などが起こるため。
3.〇 血糖コントロールの改善は、運動療法の効果である。なぜなら、HbA1cの低下、食後高血糖の改善、インスリン必要量の減少に寄与するため。
4.〇 脂質代謝の改善は、運動療法の効果である。なぜなら、中性脂肪減少、HDLコレステロール増加が期待できるため。
5.〇 心肺機能の改善は、運動療法の効果である。なぜなら、最大酸素摂取量や運動耐容能の向上が期待できるため。
1型糖尿病の原因として、自己免疫異常によるインスリン分泌細胞の破壊などがあげられる。一方、2型糖尿病の原因は生活習慣の乱れなどによるインスリンの分泌低下である。運動療法の目的を以下に挙げる。
①末梢組織のインスリン感受性の改善(ぶどう糖の利用を増加させる)
②筋量増加、体脂肪・血中の中性脂肪の減少。(HDLは増加する)
③摂取エネルギーの抑制、消費エネルギーの増加。
④運動耐容能の増強。
【糖尿病患者に対する運動療法】
運動強度:一般的に最大酸素摂取量の40~60%(無酸素性代謝閾値前後)、ボルグスケールで『楽である』〜『ややきつい』
実施時間:食後1〜2時間
運動時間:1日20〜30分(週3回以上)
消費カロリー:1日80〜200kcal
運動の種類:有酸素運動、レジスタンス運動(※対象者にあったものを選択するのがよいが、歩行が最も簡便。)
【運動療法の絶対的禁忌】
・眼底出血あるいは出血の可能性の高い増殖網膜症・増殖前網膜症。
・レーザー光凝固後3~6カ月以内の網膜症。
・顕性腎症後期以降の腎症(血清クレアチニン:男性2.5mg/dL以上、女性2.0mg/dL以上)。
・心筋梗塞など重篤な心血管系障害がある場合。
・高度の糖尿病自律神経障害がある場合。
・1型糖尿病でケトーシスがある場合。
・代謝コントロールが極端に悪い場合(空腹時血糖値≧250mg/dLまたは尿ケトン体中等度以上陽性)。
・急性感染症を発症している場合。
(※参考:「糖尿病患者さんの運動指導の実際」糖尿病ネットワーク様HPより)
95 骨粗鬆症の原因で誤っているのはどれか。
1.安静臥床
2.胃切除後
3.糖尿病
4.ビタミンA欠乏症
5.副甲状腺機能亢進症
解答4
解説
骨粗鬆症とは、骨量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気である。原因として、閉経による女性ホルモンの低下や運動不足・喫煙・飲酒・栄養不足・加齢などである。骨粗鬆症の患者は、わずかな外力でも容易に圧迫骨折(特に胸腰椎)、大腿骨頚部骨折、橈骨遠位端骨折を起こしやすい(※参考:「骨粗鬆症」日本整形外科学会様HPより)。
1.〇 安静臥床は、骨粗鬆症の原因である。なぜなら、安静臥床は、骨に対する荷重、筋牽引が減少し、骨吸収優位となるため。
2.〇 胃切除後は、骨粗鬆症の原因である。なぜなら、CaやビタミンDの吸収が低下するため。したがって、二次性副甲状腺機能亢進を介して骨吸収優位となる。
・胃全摘出術後は、胃の機能的喪失や消化管再建などに基づく様々な障害が生じる。しばしば生活支障をきたす可能性があり、対応や治療が必要である。①小胃症状、②体重減少、③ダンピング現象、④貧血、⑤骨粗鬆症、⑥逆流性食道炎、⑦下痢
3.〇 糖尿病は、骨粗鬆症の原因である。なぜなら、高血糖が続くことで骨形成を担う骨芽細胞の働きが低下し、骨の質が劣化するため。また、血管障害により骨への血流が減少し、修復が遅れることも要因の一つである。
4.〇 ビタミンA欠乏症は、骨粗鬆症の原因とはいえない。一方、ビタミンA過剰により、骨粗鬆症の原因となる。なぜなら、ビタミンA過剰は、骨の形成を担う骨芽細胞の働きを弱め、骨を壊す破骨細胞の活動を促進するため。その結果、骨密度が低下し、骨粗鬆症や骨折のリスクが高まる。特にサプリやレバーの過剰摂取に注意が必要である。
5.× 副甲状腺機能亢進症は、骨粗鬆症の原因である。なぜなら、原発性副甲状腺機能亢進症により、骨吸収が亢進されるため。特に、副甲状腺ホルモンであるパラトルモンが血液のカルシウムの濃度を増加させるように働く。
・骨吸収とは、その名の通り骨組織の吸収であり、つまり、破骨細胞が骨の組織を分解してミネラルを放出し、骨組織から血液にカルシウムが移動するプロセスである。