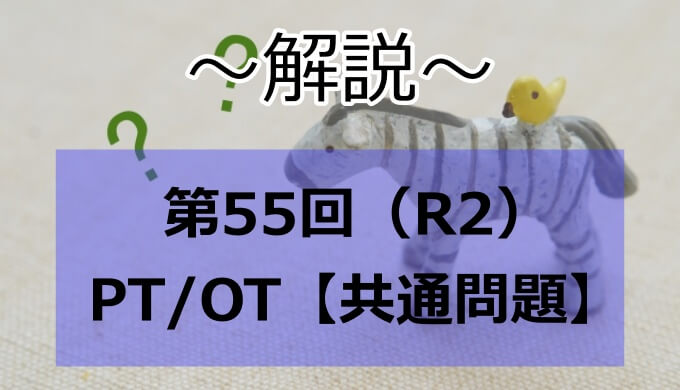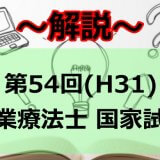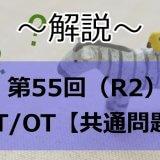この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
96 認知症患者に対して行われるのはどれか。2つ選べ。
1.音楽療法
2.内観療法
3.森田療法
4.精神分析療法
5.リアリティオリエンテーション
解答1,5
解説
1.〇 正しい。音楽療法は、認知症患者に対して行われる。
・音楽療法とは、「音楽のもつ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障害の軽減回復、機能の維持改善、生活の質の向上、問題となる行動の変容などに向けて、音楽を意図的、計画的に使用すること(日本音楽療法学会)」と定義されている。メロディを聴き、リズムに体を揺らし、歌詞を思い出し、声を出すなど、音楽を通してさまざまな脳の部位が協調して働くことによって、脳が活性化されるため、認知症患者に対して行われる。
2.× 内観療法より優先されるものがほかにある(認知症に対し思考負荷が高い)。
・内観療法とは、吉本伊信の内観法(修養法の一種)を基にした精神療法で、「してもらったこと」、「して返したこと」、「迷惑をかけたこと」の3点に絞って具体的な事実を想起する。両親に勧めるものとして適切とはいえない。内観療法は、アルコールや薬物依存・適応障害の治療法として効果があるといわれている。
3.× 森田療法より優先されるものがほかにある(認知症に対し思考負荷が高い)。
・森田療法とは、目的・行動本意の作業を繰り返すことにより、症状にとらわれず、症状を「あるがまま」に受け入れながら生活できるようにする方法である。対象疾患は、神経症性障害などである。
4.× 精神分析療法より優先されるものがほかにある(認知症に対し思考負荷が高い)。
・精神分析療法とは、自由連想法により無意識のうちに抑圧されていた葛藤を意識化させ、洞察し解決に向かわせる手法である。フロイトにより開発されたもので、成人の神経症性障害に適応となる。精神療法の代表的なものである。
5.〇 正しい。リアリティオリエンテーションは、認知症患者に対して行われる。見当識(時間・場所・人物)を日常会話の中で確認し、安心感と自立度の維持を図る。病棟・施設・在宅で日常的に実施する。
「今がいつなのか?」「ここはどこなのか?」「周りの人が誰なの
例)「〇〇さん、ちょっと外を見てください、今日はいいお天気で
97 統合失調症において予後が良いのはどれか。
1.男性
2.若年での発症
3.潜行性の発症
4.強い陰性症状の存在
5.明らかな発症誘因の存在
解答5
解説
統合失調症は、1000人に数人というほどの発症率である。発症のピークは、男性は15~24歳。女性は25~34歳である。男女比は1:1、女性は男性に比して初発年齢が遅いこと、予後が良いこと、閉経期にもう一つの発症ピークがあることなどから女性ホルモンが病態に抑制的に作用している。治療は、抗精神病薬による薬物治療が主となり補助的にリハビリテーションなども行う。統合失調症の予後予測因子は、早期治療と治療の継続性である。発病早期に薬物治療を導入すると、予後がより良い。
予後良好な因子:病前機能が良好であること(例,優秀な学生,しっかりした職業歴)、発病が遅いか突然であること、統合失調症以外の気分障害の家族歴があること、認知障害がごく軽微であること、陰性症状がほとんどないこと、精神病未治療期間がより短いことなどがあげられる。
予後不良な因子:発症年齢が低いこと、病前機能が不良であること、統合失調症の家族歴があること、陰性症状が多くみられること、精神病未治療期間がより長いことなどがあげられる。
(※参考:「統合失調症」MSDマニュアル様HPより)
1~4.× 男性・若年での発症・潜行性の発症(病気の多くは症状が出現して発見されるが、症状があきらかでない状態で、気がつかないうちに病気が進行すること。)・強い陰性症状の存在(意欲・自発性の低下、感情の表出の低下など、ある程度客観的に評価できるもの)は、予後不良な因子である。
・陽性症状とは、幻覚、妄想、自我障害など、患者が体験するもの(出てくる症状)である。
・陰性症状とは、意欲、感情、会話量の低下など「失われる」症状のこと。
5.〇 正しい。明らかな発症誘因の存在は、選択肢2の潜行性の発症と対義的な言葉である。なぜなら、急性発症のことが多く、治療反応・回復が良いとされているため。したがって、発症の際に心理的(ストレスなど)あるいは身体的な誘因があるものは、その誘因がなくなれば症状が軽減しやすいため予後が良いとされる。
98 うつ病の復職支援プログラムの内容として最も適切なのはどれか。
1.認知の歪みは修正しない。
2.服薬自己管理の練習をする。
3.キャリア再構成の検討は行わない。
4.コミュニケーション能力の改善を図る。
5.配置換えをしないことを前提に職場との連絡調整を行う。
解答4
解説
復職支援プログラムとは、リワークプログラムや職場復帰支援プログラムともいう。リワークとは、「return to work」の略語。気分障害などの精神疾患を原因として休職している労働者に対し、職場復帰に向けたリハビリテーション(リワーク)を実施する機関で行われているプログラムである。
【医療リワークプログラムの実施形態の定義】
(1)個人プログラム:文字や数字、文章を扱う。机上での作業を一人で行い、集中力や作業能力の確認、向上を図る
(2)特定の心理プログラム:認知行動療法やグループカウンセリングなど、特定の心理療法を実施
(3)教育プログラム:症状の自己理解を主目的とし、主に講義形式で病気について学ぶ
(4)集団プログラム:実際に役割分担をしての共同作業などを行い、対人スキルの向上などを目指す
(5)その他のプログラム:運動、個人面談等、(1)~(4)のいずれにも該当しないプログラム
(※引用:「リワークプログラムについて」日本うつ病リワーク協会様HPより)
1.× 認知の歪みは修正「する」。なぜなら、認知の歪みを修正することで、問題解決・ストレス対処を身に着け、働き続けられることが期待できるため。
・認知のゆがみとは、①全か無か思考、②一般化のしすぎ、③心のフィルターなどの思考の偏りである。それに対して、認知行動療法を用いて思考の偏りに修正する方法が一般的である。
2.× 服薬自己管理の練習をする優先度は低い。なぜなら、服薬は復職段階ではすでに安定していることが前提であるため。プログラムにより継続の工夫や副作用モニタリングを扱うことはあるが、中核目標ではない。
3.× キャリア再構成の検討を「行う」。なぜなら、キャリア再構成を行うことで、働き方の見直し、症状に配慮しつつ働き続けられる環境調整を整えることができるため。
4.〇 正しい。コミュニケーション能力の改善を図る。なぜなら、コミュニケーション能力は、復職・職場定着に直結するスキルであるため。集団プログラムにて対人スキルの向上などを目指す。
5.× 「配置換えをしない」ではなく、配置換えも選択肢の一つとして、職場との連絡調整を行う。なぜなら、配置換えは、症状に配慮しつつ働き続けられる環境調整に寄与するため。業務内容・時間・配置などに配慮し、再発防止の観点からもアプローチする。
99 解離性障害の治療として正しいのはどれか。
1.破壊的行動を許容する。
2.空想の肥大化について指摘しない。
3.有害な刺激を無理に取り除かない。
4.速やかに心的外傷の直面化を図る。
5.病気と治療について明確に説明する。
解答5
解説
解離性障害とは、心的外傷体験・人間関係などを原因として、それらの問題を抱えきれず、記憶・同一性の統合を失うことで当面の苦痛を回避する行動をいう。健忘、混迷状態、解離性同一性障害(多重人格)、Ganser症候群(偽認知症の一つで的外れ応答が特徴)などがみられる。疾病利得が根底に存在する。初期治療の目標は、患者との信頼関係を築き、安全な環境を提供することに重点を置くべきである。
1.× 破壊的行動を許容する必要はない。むしろ、危機管理と明確な境界設定が必要である。許容することで、症状維持・二次的利得を強める恐れがある。したがって、行動に関する責任の所在を明確するように努めることが大切である。
2.× 空想の肥大化について「指摘する」。なぜなら、指摘しないことで、出来事の解釈が誇張され、現実との境界が曖昧になる恐れがあるため。ただし、指摘の仕方も頭ごなしに否定せず、安心できる場で現実検討を穏やかに支援する。
・空想の肥大化とは、ストレスや不安を背景に、頭の中の想像がどんどん膨らみ、事実以上に本当らしく感じられてしまう状態である。
3.× 有害な刺激は「多少無理しても取り除く」。なぜなら、安全確保が最優先であるため。明らかな有害刺激は可能な範囲で除去・距離化する。
4.× 速やかに心的外傷の直面化を図る必要はない。なぜなら、安定化前の早期直面化は、さらなる症状の悪化につながりかねないため。まずは危機回避であり、段階づけ(安定化→処理→統合)が原則である。
5.〇 正しい。病気と治療について明確に説明する。なぜなら、病気の仕組み・誘因・治療方針をわかりやすく共有することで、一緒に治療に参加し治療者との信頼関係が築きやすいため。再発予防にも寄与する。
100 てんかんに伴う精神症状として適切でないのはどれか。
1.粘着性
2.爆発性
3.疾病利得
4.不機嫌状態
5.もうろう状態
解答3
解説
てんかんとは、脳の神経の電気信号が過剰に発射され、意識障害やけいれん発作を繰り返す病気である。発作が起こる前に、精神症状(怒りっぽさ)があらわれることがある。精神症状の多くは複雑部分発作の際にみられる。さらに、発作後に不安感や興奮状態などがみられることもある。
【てんかんに関連した精神症状】
・意識障害:意識が変わる(意識変容)、もうろうとする、意識が混濁する。
・感情障害:不機嫌になる、怒りっぽくなる(爆発性)。
・性格変化:まわりくどくなる(迂遠、冗漫)、しつこくなる(粘着性)。
・精神病様状態:幻覚がみえる、妄想てきになる。
・行動異常:無意味な動作を繰り返す(自動症)、異常な行動、暴力的、犯罪。
1.〇 粘着性は、てんかんに伴う精神症状である。特に、間欠期にみられる。
・粘着性とは、考えが切り替わりにくく話が冗長になる傾向。
2.〇 爆発性は、てんかんに伴う精神症状である。特に、前駆期、間欠期にみられる。
・爆発性とは、易刺激的、易怒的=怒りっぽさ、攻撃的と同義である。
3.× 疾病利得は、てんかんに伴う精神症状ではない。特に、解離性(転換性)障害にみられる。
4.〇 不機嫌状態は、てんかんに伴う精神症状である。前駆期や発作後にみられる。
・不機嫌状態は、易刺激性、抑うつなどの症状が一定期間持続することである。
5.〇 もうろう状態は、てんかんに伴う精神症状である。特に、発作時、発作後にみられる。
・もうろう状態とは、意識がはっきりせず見当識が乱れる状態である。
類似問題です↓
 【共通のみ】てんかんについての問題「まとめ・解説」
【共通のみ】てんかんについての問題「まとめ・解説」
※問題の引用:第55回理学療法士国家試験、第55回作業療法士国家試験の問題および正答について
※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。コメント欄にて誤字・脱字等、ご指摘お待ちしています。よろしくお願いいたします。